| 高原に群がる蝶「アサギマダラ」 |
| 更新日:2006年08月28日 | カテゴリー: 八ヶ岳日誌 |
|
約20年ほど前、身近に見る蝶に興味を持ち追いかけた時期がありました、そのキッカケになったのがアサギマダラでした。
6月の気持ちよく晴れ渡った休日、蓼科高原の山野草観察に一人山歩きの途中、道端に腰を下ろし一休みしていた私の目の前を フワリ フワリ と優雅に舞う変った色の蝶が近くの花に止まりました、そっと近寄って見ると今まで見たことも無い不思議な翅の色に見入ってしまい、帽子をとつて捕獲を試みましたが察知され、あっという間に一気に空高く舞い上がってしまいました。
蝶の翅を透して空が見えるような透き通った青色と後翅の自然の茶色が高い空の青に吸い込まれていくようで暫くの間感激し、高く滑空してゆく姿を仰いでいました、帰宅してから子供の昆虫図鑑でこの蝶をアサギマダラと知りました。
毎年、初夏から秋にかけて当地でも良く見かける蝶ですが9月頃は特に標高の高い山肌のヒヨドリグサに群がる姿をみることができます、オスのアサギマダラはヒヨドリグサで吸蜜することによりオスとしての成熟ができるようです。
その後寒くなる前に気流に乗って暖かい南を目指し、時には1ヶ月以上かけて1,000Km以上の長旅をして越冬地に到達するようです。
来年の6月ころには再び北上して元気な姿を見せてくれることでしょう。
今、私のデスクトップの背景には今年の若いアサギマダラの美しい姿が映っています。

御小屋山の中腹に集まりはじめたアサギマダラ(H17.9.13撮影)

ヒヨドリグサを吸蜜するアサギマダラ(四季の森こけもも平 H18.8.17撮影)
|
| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | Y |
| 多留姫(たるひめ)の滝 |
| 更新日:2006年08月23日 | カテゴリー: 周辺情報 |
|
暫くご無沙汰してしまいまして申し訳ありませんでした。
今回は四季の森から車で10分くらいの程近い茅野市の名勝「多留姫(たるひめ)の滝」をご案内致します。
諏訪湖にそそぐ上川の支流、柳川(やながわ)が大泉山南麓の岩場を流れ落ち、小断層下流の岩場が侵食されニ段の滝が形成されてこの滝ができたと言われます。上の段の滝は、幅、高さともに9メートル、下の段の滝は高さ3メートル、幅は1メートルほどで杉木立を抜けて吊り橋から眺める景色は残暑を凌ぐには格好かもしれません。
滝の右、段丘状の斜面には上諏訪村(現諏訪市)生まれの島木赤彦の「高きを見ずや八ヶ岳 深きを見ずや諏訪の湖 山と水との中空に 白糸さらす多留姫や 滝のしぶきに常ぬれて千代の緑の色深き 大泉山の山松に 藤波かかる春のくれ」(玉川村の歌)と刻まれた歌碑があり、また大泉山への遊歩道沿いに多くの句碑、歌碑が立ち並んでいる。
滝の北側の遊歩道をほんの少し登った一角に「載酒亭」(さいしゅてい)と称するあずまやがあり滝を眼下にみおろしながら休憩できる。現在のあずまやは最近建てたものですが、かつての「載酒亭」は昭和の前半まで対岸の滝をみおろせる場所にあり、和室、縁側、トイレなどがあり地域住民が事あるごとに集まり、藤の花を観賞したり歌を詠んだりしながら酒を酌み交わしたようです。ちなみに、本来の「載酒亭」の意味は、「滝にお酒をさしあげる」との意だったようです。肝心の「多留姫」の由来が後になりましたが、多留姫は信濃の国一の神、諏訪明神の御子とされ滝の南岸の杉木立を境内として多留姫神が祀られた社があり、およそ750年前にはすでに祀られ注目されていたようですが、現在一般的にはこの神社よりも滝の方が人に知られているようです。
駐車場奥の遊歩道入り口に「多留姫文学自然の里ご案内」と書かれた案内看板が設置されていますが案内地図で感じるほど距離はありませんので気軽に展望台までの往復はいかがでしょう。

吊り橋から見る滝の景色

多留姫神社
|
| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | E |
| 建売別荘見学会のご案内 |
| 更新日:2006年08月09日 | カテゴリー: イベント・観光情報 |
|
下記日程にて建売別荘の見学会を開催いたしますので、是非お出かけ下さい。
開催期間中はお楽しみプレゼントを用意していますので、お気軽にご来場下さい。
1、開催日 平成18年8月10日(木)〜平成18年8月16日(水)まで
2、完成済みの建売別荘(2棟)
しらかば平W− 8区画⇒4,150万円(消費税込)
からまつ平I−14区画⇒3,250万円(消費税込)
3、工事中建売別荘(1棟)
からまつ平L−24区画⇒3,480万円(消費税込)
完成予定(平成18年11月30日)
4、売建別荘(1棟)ご契約後、建築に着手します
こけもも平6−12区画⇒4,380万円(消費税込)
|
| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | 管理者 |
| しらかば平を流れる「一之瀬汐」の知られざる歴史 |
| 更新日:2006年08月03日 | カテゴリー: 周辺情報 |
|
オーナーの皆様が散策されている一之瀬汐についてお知らせ致します。
一之瀬汐開削の祖、坂本養川翁は元文元年(1736)諏訪郡田沢村(現茅野市)に生まれました。 28歳の時尾張、伊勢、紀伊、摂津、大和、山城の諸国で水利の実情を見聞し、後に江戸へ出て水利や農地開発を学び郷里に戻りました。貧しい八ヶ岳山麓一帯を稔り豊かな郷にするために水利、開田計画の請願を10年間もの歳月にわたり高島藩に行ったと言われております。高島藩から汐筋開発許可の下りたのは天明5年(1785)です。坂本養川翁は翌、天明6年一之瀬汐開削に着手されました。養川翁は杖突峠に登り提灯や「たいまつ」により高低測量を行ったと言われております。八ヶ岳阿弥陀岳に源流を有する一級河川柳川から取水、原村と茅野市宮川地籍の一部の耕地を潤して、原村内の阿久川から宮川を経て諏訪湖に注ぐ「農耕の命の水」として今もなお季節天候を問わず汐元の水の管理が伝承されております。
参考文献 坂本養川先生 諏訪地方事務所。諏訪耕地協会

220年の歴史を育み流れる一之瀬汐 (H18.8.2撮影)

汐役員による草刈(7月22日)後の一之瀬汐 (H18.8.2撮影)
|
| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | S |
| W-8 建売別荘(しらかば平)が完成致しました |
| 更新日:2006年08月02日 | カテゴリー: 別荘情報 |
|
今回完成した建売別荘は、四季の森には今までなかったような斬新かつ個性的な建物に仕上がりました。
特に外観は、外壁と軒裏天井のコントラストが目を見張らせ、また、リビングからフラツトで続く一体化したアウトドア感覚のテラス、そのテラスから南に張り出したウッドデッキ、それに正面のプロポーションをゆとりある車庫の屋根が一段ときわ立たせています。
内部は、土間感覚、テラコッタ風タイルのリビングに設置されたシェルバーンの薪ストーブが冬を待ち遠しくさせてくれます。もちろん床暖房も装備しています。
土足でよし、スリッパに履きかえてもよし、テラスと合わせてこの辺りの使い勝手は自由気ままにオーナー様次第と言ったところです。
高原の「涼」を求めながらのご一見はいかがでしょうか、この夏一番のお勧め物件です。
スタッフ一同お待ちしております。

竣工建築全景

リビング タイルの床はテラスへとフラットで続く
|
| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | T |
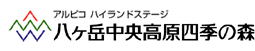
![]()
![]()