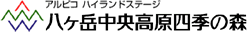四季の森ニュース

立夏
- 更新日2021年05月06日
- カテゴリ四季の森だより
5月6日(木)
今日は雨上がりで爽やかに晴れました。
ただ朝のうちは、四季の森周辺は深い霧の中でした。
こけもも平の今朝の最低気温 8.9℃ 6:10観測
今朝は暖かな朝になりました。これくらい暖かだと朝から体が動かしやすいですね。
ただ個人的には、もう少し寒いほうがシャキッとするのですが。
今朝の八ヶ岳方面 立沢地区大規模水田地帯にて撮影
八ヶ岳方面は霧に包まれていました
西山方面には雲海が発生していました
家を出発した時には、雪を頂いた富士山が美しく見えていたのですが、立沢からは霧で見えません。
地面付近を霧が漂っています
さて、昨日は「端午の節句」でした。
「端午」は、本来は月の最初の「午(うま)」の日を意味していますが、
「午(うま)」は「ご」とも読み、「5」に通じることから「5日」を指すようになり、
「5」が重なる5月5日を「端午の節句」と呼ぶようになったのだそうです。
日本の端午の節句は、奈良時代から伝わる風習なのですが、もともとは女性の行事だったのだとか。
田植えの時期である5月の最初の午の日に、稲の神様に豊穣を祈願する早乙女と呼ばれる若い娘達が、
小屋や神社にこもり、田植えの前に穢れを祓って身を清める神聖な儀式の日だったようです。
現代でも、菖蒲やヨモギを軒に吊るしたり、菖蒲湯に入る風習が残っていますね。
平安時代になると、端午の節句に、馬の上から矢を射たり、競馬をするなどの勇壮な行事が行われるようになりました。
そして、菖蒲が「勝負」や「尚武」と同じ読みであること、また菖蒲の葉の形が剣を連想させることから、
男の子が菖蒲を身に着けたり、菖蒲で作った兜で遊ぶようになり、
鎌倉時代頃から男の子の節句とされ、甲冑、武者人形を飾り、鯉のぼりを立てて男の子の成長を祝うようになりました。
江戸時代に入ると、幕府が公的な行事として定めたことから庶民にも広まっていったようです。
端午の節句には、鯉のぼりを飾るご家庭もありますが、
黄河の急流にある竜門と呼ばれる滝を多くの魚が登ろうとしたところ、
鯉だけがその滝を登り竜になることができたという中国の故事にちなみ、
鯉が立身出世の象徴として日本に伝わり、男の子が将来立派に出世するように願いを込めて
鯉のぼりを飾るようになったのだそうです。
鯉のぼり
そして、5月5日からは二十四節気の7番目の節気となる「立夏」になりました。
夏の気配が立ち上がってきたような時期という意味になります。
暦の上での夏の始まりで、この日から立秋の前日までが夏季ということになりますが、
本格的な夏はまだ先で、気温もさほど高くならないものの、陽の光は強く、「光の夏」とも呼ばれることがあります。
こうした光を受けて、野山の草や木々の青葉もどんどん深みを増していきます。
深山地区環境保全林も緑が濃くなってきました
オオヤマザクラは既に葉桜に
でも、まだコブシも咲いています
朝霧が発生した四季の森周辺でしたが、霧はすぐに晴れて、爽やかな青空が広がりました。
気温も朝から高めでしたので、日中は暑いくらいです。
センター前のヤマザクラが満開です
青空とのコントラストが美しい
カラマツも緑が濃くなってきました
別荘地内ではオオカメノキも咲き始めています
オオヤマザクラが見頃の場所もあります
ジューンベリーでしょうか、満開です
新緑のシラカバ
今日は日差しもたっぷりで、まさに光の夏です。
販売管理センター 25℃ 15:50現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 19.9℃ 15:50現在
今日は、センターでも25度の夏日、こけもも平でも14時に20..4度を観測しました。
いよいよこけもも平でも20度台まで気温が上がるようになってきたんですね。
今日のセンター
今日のまるやち湖 11時半頃撮影