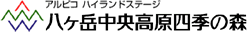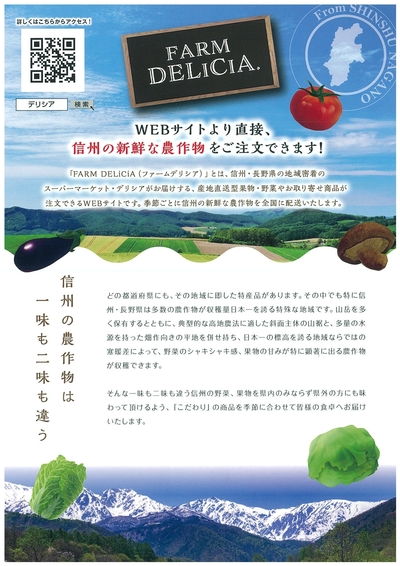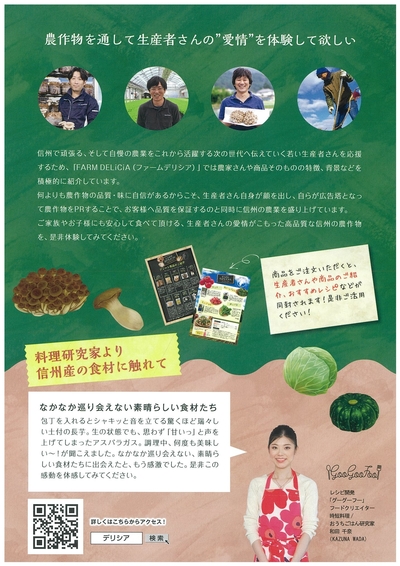四季の森ニュース

- 更新日2021年06月14日
- カテゴリ四季の森だより
今朝方はシトシトというよりやや強めに降っていた雨ですが、徐々に小雨になり、
通勤時間帯頃にはほとんど止みました。
時折、青空も見えるようになったのもつかの間、厚い雲に覆われていた午前中です。
それでも森のハルゼミは賑やかに鳴いています。
今朝の八ヶ岳方面
富士見町立沢の牧場上空も一時的に青空が見えました
さて、昨年のこの時期にご紹介したのが、毒を持たないキアシドクガです。
幼虫はミズキやクマノミズキの葉が好物で、ミズキは丸坊主になってしまいます。
5月29日のミズキの様子
実はこのミズキは、私の家の近くにある別荘地に生えていたもので、
所有者が変わり、6月に入ってすぐに木の伐採が行われました。
伐採後のミズキ(6月5日撮影)
水の木という名の通り伐採した木から水のような樹液が大量に流れ出ていますね。
少し気の毒に思いますが、日当たりなど考えますと仕方がないのかもしれないですね。
そして、葉を食べていたキアシドクガがどうなったのか気になり、周辺を観察してみますと、
サナギがいましたが、ほんの数匹しか確認できませんでした。
そして昨日、ひらひらと飛んでいるキアシドクガを見つけました。
キアシドクガ(画像真ん中)
例年この時期になるとキアシドクガの美しい乱舞が見られるのですが、今年は1匹だけで舞っていました。
ここは寂しくなってしまいましたが、山のあちこちでキアシドクガの乱舞が見られる時期になっています。
そして、ミズキと一緒に伐採されたのがこちら。
葉がないので樹種ははっきりしませんが、確かこの辺りにヤマボウシがあったような。
オレンジ色の樹液が目立ちますね。
伐採された木からこのような樹液が出ているのをたまに見かけることがあります。
木が流している血や涙のようにも見えてとても痛々しく感じるのですが、
実はこれは「樹液酵母」と呼ばれるものです。
主に糖分の多いカエデやミズナラなどの広葉樹の切り株から流れ出た樹液に天然の酵母が付着して発酵し、
そこに赤カビがついて繁殖しコロニーを形成したものなのだそうです。
酵母が発酵したものなので、天然のお酒ができることもあり、
赤カビに毒性がなければ食用にすることもできるのだとか。
ちょっとグロテスク過ぎて試してみることはできませんでしたが、
ネットなどで検索すると、食べてみたという方もいらっしゃるようです。
また、リスや蜂も好んで食べるのだそうです。
糖分が多いということなので甘いのかもしれませんね。
樹液酵母は、今やパンやビールなどにも使われることも多くなっています。
四季の森周辺では、
ニセアカシアの花が咲き始めています。
ハコネウツギも見頃です
キバナノヤマオダマキ(もみの湯付近で撮影)
ムラサキツユクサ(もみの湯付近で撮影)
レッドキャンピオン(もみの湯付近で撮影)
樅の木桜公園のヤマボウシ
その中の1本の木には、白とピンク色の花がミックスされています。面白いですね。
雷も轟いた午前中でしたが、雨は降りませんでした。
お昼頃からは一時的に天気が回復し薄日も差すようになったものの、
また雲が広がって雨が降り出しています。非常に不安定な天候です。
販売管理センター 22℃ 13:30現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 16.8℃ 13:30現在
関東甲信地方は、平年より1週間ほど遅れて梅雨入りしました。
これから雨の日が多くなっていきますね。
今日のセンター
昨日の夕方、しらかば平の路上で虫と格闘している鳥がいました。
うっかり放してしまい追いかけていましたが、結局捕まえられたのか気になります。
- 更新日2021年06月13日
- カテゴリ四季の森だより
朝は薄日が差していたのですが、9時半頃から雨が降り出しました。
ただ雨はそれほど強くなく、降ったり止んだりを繰り返しています。
明け方は雲が広がっていたので暖かいものの、日中は日が差さないので気温は上がらず、
建物内にいると少しひんやりと感じますが、過ごしやすい気温です。
今朝の八ヶ岳方面 低い雲が広がっています
入笠山方面
さて、四季の森周辺の様子です。
エコーライン沿いでは、ヤマボウシが見頃になっています。
観察してみましたが、まだ中心の花は咲いてはいません。
また沿道などでは、
ノイバラも見頃になっています。
そして、八ヶ岳自然文化園では、
今朝のまるやち湖
ニッコウキスゲが咲き出していました
もうそんな時期なんですね。
原村ペンションビレッジ内では、
サンショウバラが満開です
葉がサンショウの葉に似ていることから名付けられたそうです。
日本の固有のバラです。
別荘地内でもいろいろな花が咲いていますが、ちょっと見落としてしまいそうな花を発見しました。
オオツリバナです。こけもも平で撮影しました。
ツリバナ、オオツリバナは、ニシキギ科ニシキギ属の落葉低木です。
名前の通り、花や果実を吊り下げているような姿から名付けられています。
1㎝にも満たない淡い緑色や淡い紅色の小花をたくさん咲かせますが、色が淡いのでそれほど目立たず、
車で走っていると見つけられないかもしれません。
ツリバナはやや赤みのある花で、オオツリバナは赤みのない黄緑色の花が咲き来ます。
花はそろそろ終盤のようですが、
夏から秋にかけて真ん丸な実をつけます。
つり下がった実が熟すと赤くなり、くす玉のように割れて縁に赤い種が目立つようになります。
赤い実は茶花にも重宝されるようです。
また、秋になったら赤い実を撮影してみたいと思います。
その他別荘地内で見つけた花々です。
ベニバナイチヤクソウ
スモークツリーでしょうか。雄花のようです
フウロソウ
フタマタイチゲ
ウツギ
ヤグルマソウ(ユキノシタ科)
カラコギカエデ
サクラの実
昨日ですが、家で小さなカタツムリを見つけました。
小指の先よりも小さい可愛いカタツムリでした。
カタツムリを見ると梅雨だなぁと感じますね。
今のところ雨はそれほど降っておらず、15時現在道路は乾いている状態です。
販売管理センター 21℃ 15:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 16.8℃ 15:00現在
雨は、今晩から明日の朝にかけて降るようです。
明日も愚図ついた天気になりそうですが、そろそろ梅雨入りでしょうか。
今日のセンター
森林軌道見学者駐車場のトチノキ
- 更新日2021年06月09日
- カテゴリ四季の森だより
今朝は8度台まで気温が下がったので、ひんやりと感じましたが、
雲一つない青空が広がり、風がそよそよと吹いて気持ちのよい天気になっています。
今朝の八ヶ岳
今朝は北アルプスも薄っすらと見えました。
富士山も昨日と同じようにぼんやりと見えていました。
遠くの山々は霞んでくっきりとは見えなくなる時期ですね。
さて、周辺のヤマボウシですが、エコーライン沿いの日当たりのよいところなどは総苞片が白くなり、
遠くからも目立つようになってきました。
別荘地内のヤマボウシはまだ緑がかっているものがほとんどです。
深山地区環境保全林の中のヤマボウシ
すごい花付きです。
花柄が長いので、
白いチュチュを着たバレリーナ達が群舞しているようにも見えますね。
朝日が当たって輝いています
ヤマボウシは、「山法師」と書きますが、総苞と中央の花を合わせた姿が
比叡山延暦寺の頭巾をかぶった山法師になぞらえて名付けられたと言われています。
真ん中の花の部分はまだ咲いてはいません
総苞片は葉に分類されるのですが、
ヤマボウシの場合は総苞片を合わせて花として捉え、便宜上、総苞片を花びらと呼びます。
通勤途上の原村の民家の庭先には赤いヤマボウシが咲いていました。
絵具でぼかして色をつけたようです
ヤマボウシは、花も実も紅葉も可憐で美しいので、四季を楽めるとても魅力ある樹木ですね。
これから徐々に標高の高いところへ花の見頃は移っていきます。
そして、もみの湯上のモミジ並木では、
モミジの翼果が色づいてきました
またモミジ並木の途中には、
バイカウツギが咲きだしています
バイカウツギとアヤメのコラボレーション
モミジ並木とアヤメ
アヤメもあちこちで見頃になっています。
今日はカラッとしているためか、爽やかな日中が続いています。
お散歩には最適な陽気です。
販売管理センター 24℃ 14:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 21.7℃ 14:00現在
明日は今日よりも更に気温が上がりそうです。蒸し暑くないといいのですが。
今日のセンター
センターのモミジ 非常に小さな種が実っていました
- 更新日2021年06月08日
- カテゴリ四季の森だより
昨日の原村の気温は26.9度で、風も弱く蒸し暑い陽気でした。
今日は、薄い雲はあるものの朝から日差しがあったので、
昨日よりも暑くなるのではと予想していたのですが、
お昼頃から雲が広がってきましたので、気温もそれほど上がっていません。
今朝の八ヶ岳
今朝の富士山 うっすら見えます
さて、二十四節季は6月5日より「芒種(ぼうしゅ)」に変わりました。
「芒種」という言葉はあまり馴染みがありませんが、
「芒」は「のぎ」と読み、麦や稲などイネ科植物の穂先にある針のような毛のことを指しています。
この時季は、この「芒」のある植物の種を蒔いたり麦の刈り入れや田植えを行うのに
適した時期とされてきました。
というのも、昔は稲の苗を水田で育てていたため現在よりも生育が遅く、
田植えは6月に入ってから行うものでした。
また、「芒種」は夏至の前日までの期間になりますが、
梅雨の季節にあたることから、蒸し暑さを感じるシーズンでもありますね。
沖縄県では、二十四節季のひとつ前の節季「小満(しょうまん)」から「芒種」にかけて、
雨が最も多く降る時期であることから「小満芒種」と書いて「すーまんぼーすー」と呼び、
「梅雨」のことを指しているとか。
甲信越地方はまだ梅雨入りしていませんが、来週くらいには梅雨入りするのでしょうか。
さて、八ヶ岳中央農業実践大学校の売店駐車場では、
セイヨウサンザシの花が咲き始めています
まだ満開ではないものの花はびっしりついています
セイヨウサンザシは英名で「May flower(メイフラワー)」といいます。
英語のMay(メイ)は5月のことですが、名前の通り5月頃に白や桃紅色の可愛らしい花を咲かせます。
イギリスの清教徒が信仰の自由を求めてアメリカに渡った時に乗っていた船の名前を
「メイフラワー号」と言います。そういえば歴史で習いましたね。
その船の船尾にはサンザシの花が描かれていたそうです。
サンザシの花言葉は「希望」です。
新しい土地への期待を込めてそう名付けられたのかもしれませんね。
八ヶ岳中央農業実践大学校売店付近から見る八ヶ岳
芝の緑色が眩しいです。
牛たちはのんびり
セイヨウサンザシの隣の木にスズメを見つけました。
原村の遊歩道「白樺の小径」では、
アヤメが咲き出して、レンゲツツジとの競演が楽しめます。
15時を過ぎて、空がだいぶ暗くなってきました。
夕立があるかもしれません。
販売管理センター 22℃ 15:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 18.2℃ 15:00現在
今日のセンター 13時15分頃撮影
今朝はまるやち湖に久しぶりにカルガモが泳いでいました