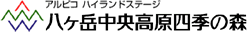四季の森ニュース

- 更新日2020年10月27日
- カテゴリ四季の森だより
今日は、朝は薄い雲に覆われていましたが、お昼現在晴れています。
四季の森周辺の紅葉もまだまだ見頃で、紅葉狩り日和が続いています。
販売管理センター 13.5℃ 13:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 10.7℃ 12:50現在
今朝の八ヶ岳
今日は西山方面が雲に覆われていました
そして甲斐駒の山頂だけがぽっかり顔をのぞかせていました
さて、今日は「テディベアの日」なのだそうです。
日本テディベア協会によりますと、テディベアの厳密な定義はないようで、
現在ではクマのぬいぐるみ全般がテディベアと呼ばれています。
ドイツのシュタイフ社、イギリスのメリーソート社に代表される伝統的なテディベアは、
手・足・首がジョイントで可動する特徴があり、良質で頑丈に作られているので、
100年以上経ってもキレイな状態で残っているものもあるのだそうです。
テディベアは、アメリカ第26代大統領ルーズベルトの愛称から名付けられています。
大統領が趣味のクマ狩りに出掛けた際、ケガをして瀕死の小熊を発見した同行者が大統領にトドメを依頼したところ、
「瀕死の小熊を撃つことはできない。放してあげなさい。」と拒み小熊の命を救ったそうです。
このエピソードは美談として、風刺画とともにワシントンポストに掲載され、
これを見たお菓子屋さんがクマのぬいぐるみを作り、大統領の愛称「テディ」から「テディベア」と名付けたのが始まりとされ、
同じ頃ドイツのおもちゃメーカーがクマのぬいぐるみを博覧会に出品し、これがアメリカのバイヤーの目にとまり、
アメリカ国内で販売したところ大ブームとなり、「テディベア」として広く愛されるようになったということです。
10月27日はルーズベルト大統領の誕生日ということで、上記のエピソードから「テディベアズデー」になっています。
蓼科テディベア美術館(白樺湖)
白樺湖畔には、テディベア美術館があります。
ファミリーはもちろん、子供から大人まで楽しめる美術館で、10月末まで「秋のくまフェス!2020」を開催中です。
ハロウィンということで、仮装した方、仮装したベアを連れた方は入館料が半額になるそうですよ。
詳細はホームページでご確認下さい。
紅葉、ハロウィン、美術館を同時にお楽しみいただける時期ですね。
今日の紅葉
立場林道(からまつ平)
そして、村道ペンション線のもみの湯からペンション上までの紅葉です。
カエデ並木もだいぶ色づいてきました
アナベルの刈り取りが行われ、サッパリしました
今日のセンター
ブルーベリーの紅葉
- 更新日2020年10月25日
- カテゴリ四季の森だより
今朝は冷え込みました。
こけもも平の観測データによりますと、4時に氷点下1度を観測しました。
いよいよ0度を下回る時期に入ってきましたので、山荘の水回りの対策はお早目にお願い致します。
販売管理センター 14℃ 14:30現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 9.5℃ 14:30現在
今朝の八ヶ岳
白い? 山は雪なのか霧氷なのか白くなっていました
西山方面
今朝は雲ひとつない富士山が見られました
さて、管理センターのドウダンツツジが見頃になっています。
24日撮影
本日撮影
ドウダンツツジは、ツツジ科ドウダンツツジ属の落葉低木です。
日本原産で、春にはスズランのような壺型の可愛らしい白い花が咲き、
秋には木全体が染まって美しくなるので、庭木としてとても人気が高い樹木です。
秋の紅葉を楽しむだけのために植栽するということも多いようですね。
枝ぶりが、結び灯台に似ていることから「灯台躑躅」となり、トウダイが転じて「ドウダン」と名付けられました。
漢語では「満点星躑躅」と書かれるのですが、中国では枝一杯に咲いた白い花を満点の星に見立てているのだそうです。
同じ仲間に、白地に赤い縞模様が入った花が咲くサラサドウダンや、赤い花のベニバナドウダンなどがあります。
皆様、世界三大紅葉樹というのをご存じでしょうか?
ニシキギ、ニッサボク、スズランノキ(ツツジ科オクシデドンドルム属)の3つなのだそうです。
ニシキギは別荘地内に植栽されているのでわかりますが、他の2つはあまり馴染みがありません。
もし見ていたとしても、その木だと気づいていないのかもしれませんね。
誰がどのように決めたのかはわかりませんが、どの木も秋になると赤く染まる樹木のようです。
ドウダンツツジも世界三大紅葉樹には入りませんが、鮮やかな赤色が美しい樹木ですね。
この時期にか見られない赤色の風景をお楽しみ下さい。
まるやち湖 12時頃撮影
まるやち湖のカルガモ
八ヶ岳自然文化園入口のカエデ 8時頃撮影
今日、スタッフが蓼科へ出向いた際に撮影してきました。
無藝荘
囲炉裏(無藝荘内部)
蓼科も現在紅葉のピークを迎えています。
蓼科はカエデが多いので、色のグラデーションが見事です。
今日は日曜日で多くの人出があったようです。
今日のセンター
抜けるような青空
明朝は更に冷え込みそうですね。
- 更新日2020年10月24日
- カテゴリ四季の森だより
昨日の雨も上がり、今朝は眩しいくらいの日射しが降り注いでいて、周辺の紅葉も光り輝いていました。
午後になり雲が少しずつ出てきました。夕方は一時的に雲が広がる予報です。
今日は風が冷たく、晴れている割には気温はあまり上がっていません。
販売管理センター 12℃ 14:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 8.2℃ 14:00現在
今朝の八ヶ岳
甲斐駒方面
西山方面
気持ちよく晴れ渡っていたのですが、富士山方面、北アルプス方面などは雲が多く山は見られませんでした。
さて、もみの湯のバス停付近のイチョウの黄葉がピークになりました。
輝く黄葉
木は数本しかないのですが、ちょうど朝日を浴びて遠くからもハッとするほどです。
国土交通省によると、全国の街路樹の1位はイチョウで57万本植えられているそうです。
ちなみに2位はサクラで52万本だそうですが、春も秋も楽しめるサクラより人気があるんですね。
イチョウは、イチョウ科イチョウ属の落葉高木です。
恐竜がいた白亜紀やジュラ紀には世界中で繁栄していた樹木ですが、その仲間の多くが氷河期に絶滅してしまい、
現在ではイチョウ科の樹木はイチョウしか残っていません。
こうしたことから、太古から今まで姿をかえずに生き残ってきたイチョウは「生きた化石植物」とも呼ばれます。
イチョウは樹齢が1000年を超えることもある長寿の木でもあり、各地に天然記念物に指定される大木が残っています。
イチョウの名は、葉がカモの足ににていることから、中国名のイーチャオ(鴨脚)が転訛したとされています。
銀杏がとれることでも知られているイチョウですが、悪臭があるので、街路樹にはオス木だけを植えることが多いのだそうです。
街路樹にイチョウが選ばれるのは、排気ガスに晒されたり過酷な環境に適した樹木であること、
そして燃えにくいため火災の際に燃え広がるのを防ぐという役割があるようです。
また、イチョウは東京都、大阪府や神奈川県などで県木にも選ばれています。
銀杏は、外皮が悪臭を放つだけではなく、アレルギー皮膚炎を引き起こす物質が含まれているので、
素手で触らないよう注意が必要です。
また、大量の銀杏を食べると嘔吐や下痢、呼吸困難を引き起こす場合もあるそうなので、食べ過ぎにはご注意下さい。
イチョウの巨木は、「ビッグイエロー」とも呼ばれ各地で愛でられています。
これから、イチョウの黄葉は山を下っていきます。
もみの湯付近は紅葉が美しくなっています。
カエデ並木
こちらはもう少しでしょうか。
温泉も恋しい季節になってきましたね。
紅葉を眺めながら、もみの湯で心も体も温まって下さい。
販売管理センター、からまつの小径散策路の紅葉です。
今日のセンター
- 更新日2020年10月22日
- カテゴリ四季の森だより
昨日の青空から一転、今日は朝から曇りになっています。
それでも午前中は山々も見渡せましたし、お昼頃には青空も見えていました。
今朝の八ヶ岳
雪も少なくなってきました。
西山方面
雲海もなくすっきりとしています。
販売管理センター 15℃ 16:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 11.8℃ 15:50現在
さて、鉢巻道路の紅葉が見頃になっています。
特に、富士見高原リゾートの周辺は、色とりどりの木々をご覧いただけます。
富士見ペンションビレッジ
週末は天気が回復するようなので、小淵沢から四季の森周辺まで、色鮮やかな森の中のドライブをお楽しみ下さい。
まるやち湖から見る八ヶ岳自然文化園
園内も紅葉が見頃になっています。
シラカバの葉が落ちてきたのでヤドリギが目立つようになりました
そして、昨日の夕方になりますが、夕日を浴びた紅葉が美しかった。
こけもも平1・2区画
しらかば平Y区画の紅葉とススキ
西日が当たるとススキがキラキラしてとても美しいです。
紅葉は、朝・昼・夕と光の加減で見え方が違いますので、それぞれの時間帯でお楽しみいただければと思います。
我が家では、
ツワブキが咲き始めました。
ツワブキは、キク科ツワブキ属の多年草です。
花の少なくなる時期に咲き始める貴重な植物で、
寒冷地では地上部は枯れてしまいますが、春になればまた新しい葉が出てきます。
葉や茎は食用にもなり、葉は薬草として使われます。
これも食用植物のコーナーで購入し植えたものなのですが、まだ食べたことはありません。(笑)
通勤途上では、
柿が色づいてきました。
今年は天候の影響か、柿は不作のようです。数えるほどしか実っていませんね。
寒冷地の柿はほとんど渋柿です。
甘柿にもはじめは渋があって、夏の気温が高くなると渋が抜けて秋に甘柿になるのですが、
寒冷地は気温が高い期間が短いので、渋が抜けきらないことが多く、甘柿の栽培に適していないのだそうです。
たまたま甘い年もあったり、次の年はダメだったりということになってしまうのですね。
今日のセンター 13時頃撮影
ドウダンツツジが色鮮やかになってきました。
- 更新日2020年10月21日
- カテゴリ四季の森だより
今日は風が冷たいのですが、朝から秋晴れの四季の森です。
久しぶりに乾いた空気に包まれています。
今日は紅葉狩りには最適な日ではないでしょうか。
今朝の八ヶ岳雲ひとつない青空です。
西山方面は山頂に少し雲がありました。雲海も少しです。
芽を出したばかりの牧草も朝日を浴びて輝いていました。
こんな秋らしい陽気が続いてくれたらいいなと思っているのですが、早くも日本の西側から下り坂のようですね。
販売管理センター 14℃ 14:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 12.2℃ 14:00現在
さて今日は、青空が美しかったので、青空と紅葉といった趣で別荘地内を撮影してみました。
シラカバ
残り少ないサクラの葉
青空がバックに入ると、何でも絵になりますね。
カラマツも少しづつですが色づいてきました。
そして、青空と山のコラボ
からまつ平からの阿弥陀岳
鉢巻道路からの天狗岳
こけもも平1・2区画からの阿弥陀岳
こけもも平7・8区画からの阿弥陀岳
青空と、紅葉と冠雪した山が楽しめる時期で、とてもお得な感じがします。
お散歩の途中、山を撮影されている方も見られました。
そして、四季の森周辺の様子です。
ペンション線鉢巻道路付近のツツジ
もみの湯上付近のカエデ並木
色づきはもう少しですね。
もみの湯バス停のイチョウ
サクラは多くの木で葉を落としていますが、まだまだ他の木々の紅葉をお楽しみいただけます。
今日は少し風があるので、カサカサと音を立てて葉が落ちてくると、一段と深まった秋を感じます。
今日のセンター
紅葉した葉が映り込まないと夏のような雰囲気ですね。