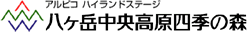四季の森ニュース

- 更新日2023年02月09日
- カテゴリ四季の森だより
今日は寒い朝でした。
身を切るような冷たい風が吹いているため、あまり気温も上がってきませんが、
日差しがあるので、目から暖かさを感じます。
今朝のこけもも平の最低気温は-8.8度(8時)でした。
また冬の寒さに戻ってしまいましたね。
今朝の八ヶ岳
入笠山方面
富士山
南アルプス(鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳、鋸岳)
今朝の北アルプスは、雲の上に山頂が少し見えるだけでした
まるやち湖
四季の森周辺では、昨晩だと思われますが雪が舞ったようです
さて、明日は朝から雪の予報で、寒気の流れ込み具合によっては警報級の大雪となる可能性もあります。
今日は寒いながらも晴れているので、信じられないような気もしますが、
寒気が残る中、南岸的圧が発達しながら通過するため、
山沿いや内陸部だけでなく、平地でも雪が降る可能性が高いようです。
特に、午後から夕方にかけて降り方が強まるとの事なので、明後日朝にはかなりの積雪が見込まれます。
高速道路の通行止め、それに伴う車の立ち往生などが発生する可能性もありますので、
ご来荘を予定されている皆様は、日程変更が無難ですので、ご検討をお願い致します。
立ち往生はいつどこで起こるかわかりません。
一旦立ち往生が発生すると、長時間にわたり動かなくなるケースも多くなっています。
雪道運転には、「タイヤチェーン」「スノーブラシ」「スコップ」、更に「滑り止め用砂」、
「軍手・ゴム手袋」、「長靴」「防寒着」「毛布」「使い捨てカイロ」、
「解氷剤」などを積んでおくことが推奨されています。
このほか、「けん引ロープ」、「ブースターケーブル」「懐中電灯」
「ウエットティッシュ」などがあると安心です。
また、1日~2日の食料や飲料水、携帯トイレなどを積んでおくのも大切です。
ご来荘の方は、最新の天気予報をご確認いただき、
道路状況には十分お気をつけ下さい。
今日はご来荘者も少なく、静かな別荘地内です。
からまつ平
からまつ平
しらかば平
しらかば平
こけもも平
こけもも平 日陰は薄っすら積雪していました
御嶽山でしょうか(こけもも平)
昼頃少し雲が出る時間帯もありましたが、再び快晴になっています。
ただ日差しの割には気温が上がらず寒い日中です。
販売管理センター 0.5℃ 14:40現在
こけもも平(標高1500m)観測データ -0.3℃ 14:20現在
雪は仕方がないですが、大雪にはならないでほしいものです。
今日のセンター
上空に飛行機雲
- 更新日2023年02月06日
- カテゴリ四季の森だより
今日も快晴です。
昨日の朝よりも冷え込まなかったのですが、
風が強く、体感温度は昨日よりも低く感じるほどでした。
日差しは強いので、日中は暖かくなりそうです。
こけもも平の今朝の最低気温は、-5.6度(6時50分)だったのですが、
原村の測候所では-8.0度を観測しています。
もしかしたらまた機器の不調なのかもしれません。
今朝の八ヶ岳
入笠山方面 こちらも雲海もなくすっきりとしています
富士山 こちらには少しだけ雲が確認できます
今朝は一段と北アルプスが美しく見えていました
まるやち湖
駐車場にオブジェを発見しました。
小さな雪だるまの集まりでしょうか。
よく見ると雪だるまに混じって可愛いハートも見えます
さて、今朝のバードフィーダーは千客万来でした
イカルですね
顔が黒いので怖い感じですが、目が見えると可愛らしいですね
おまけにスタイルもいいです
そして、イカルだと思いながら撮影したら、シメでした
こちらも強面です
近づきすぎてすぐ逃げてしまいました(残念)
ゴジュウカラ
大きい鳥がいてエサ台に近づけず、いなくなった瞬間にやってきます
こんなアクロバティックな動きができるゴジュウカラ
カワラヒワ
エサが終った頃やってきました(笑)
野鳥たちも暖かな日差しを浴びて嬉しそうです。
「千客万来」とは、多くの客がひっきりなしに来て絶え間がないことを表す四字熟語ですが
対義語は「閑古鳥が鳴く」とか「門前雀羅(もんぜんじゃくら)」になります。
「門前雀羅」は、人の往来がなく寂れて廃れている様子、
また昔の勢いがなくひっそりしている様子を表す言葉です。
雀羅とは、雀を捕らえる網のことですが、
訪れる人がおらず、門の前には網で捕まえられるほど雀が群れているという意味になります。
「門前雀羅を張る」というように使われますが、
これは、中国の「史記」に由来する故事成語です。
前漢王朝時代の中国に翟公(てきこう)という人物がおり、
高い地位に就いている時には、屋敷に訪問客が絶えませんでしたが、
左遷された途端に誰も来なくなり、
門外雀羅(門の外に雀取りの網をはっても大丈夫)というありさまでした。
その後高い地位に復帰すると、またぞろぞろと人々が押しかけてきたので
翟公はあきれてしまったそうです。
この話から、唐王朝時代の詩人、白居易(はくきょい)が、
左遷された人からすぐに離れていく世の人の情を
「賓客またすでに散り、門前雀羅を張る」とうたった言葉が由来となっています。
「門前雀羅」を張ることなく、
「千客万来」「門前成市(もんぜんせいし)」となるよう、
エサ置きを忘れずにしないといけませんね(笑)
昨日帰宅途中の月です。ほぼ満月でした。
立沢大規模水田地帯からの撮影ですが、ちょうど阿弥陀岳山頂の上に月が出ていました
八ヶ岳から昇る月が撮影できる場所はとても貴重だと思います。
我が家まで進むと全く違う場所に月が出ていますから。
午後は薄雲が広がりましたが、暖かな日差しが届いていて、
今日はずいぶん気温が上がり、雪解けもだいぶ進みました。
センター付近は西日が当たるので、10度は超えたと思われます。
販売管理センター 9℃ 16:20現在
こけもも平の気象データは調整中のため確認できません。
天気は下り坂で、今晩から雲が広がり、
明日の昼前後に少し晴れとなりますが、曇りの予報になっています。
もしかしたら雪が降る可能性もあるようなので、ご注意下さい。
今日のセンター 15時過撮影
まるやち湖 15時撮影
- 更新日2023年02月05日
- カテゴリ四季の森だより
霞もなく澄み切った空が広がっている本日、
朝は厳しい冷え込みでした。
こけもも平の最低気温は、-9.2度(7時10分)です。
このところ、前日の夜はそれほど冷えていないのに、
朝方ぐぐっと冷え込むようになっています。
夜は、日が伸びてきたので暖かさが残っているのかもしれませんね。
今朝の八ヶ岳
入笠山方面 雲海が少し出ています
富士山
今朝は快晴なので払沢農村広場まで足を伸ばしてみました。
八ヶ岳とわらにょう
峰の松目・硫黄岳 横岳 阿弥陀岳
蓼科山 北横岳
霧ヶ峰・車山
茅野市街地方面 北アルプスだけは雲があり見えていません
まるやち湖
駐車場から見る青空
昨日は立春でした。
暦の上では春になりましたね。
今日はそんな春を感じられるような穏やかで、暖かな日中です。
タイトルをどうしようかとても悩みました。
暦は春ですが、寒中ではないもののまだまだ寒い時期ですし、
春なのに冬という言葉を使ってもよいものか、言葉選びはとても難しいですね。
「冬温し(ふゆぬくし)」は冬の季語で、寒い冬にふと暖かくなる日のことです。
冬日和、冬晴れなどとも言いますね。
こんな天気が続いてくれるといいのですが、希望通りにはなりません。
これからは天気が変わりやすくなるようです。
暖かい日も増えてきますが、雪も多くなる時期です。
天気予報をご確認の上、ご来荘下さい。
今日の別荘地内です。
からまつ平
先日、この坂で滑って派手に転びました。雪の下が凍結していますのでお気をつけ下さい
からまつ平
しらかば平
しらかば平
こけもも平
こけもも平
共用道路
日中は、北アルプスがよく見えるようになりました (しらかば平)
朝は木の影で雪が縞模様に見えます
センターのオオヤマザクラ
まだまだ桜のつぼみは固いです
さて、明日の明け方(3時半前後)は満月です。
地球から最も遠くなる満月で、マイクロムーンと呼ばれます。
2023年に最も近い満月は8月ですが、それと比較すると視直径が12%小さく見えるそうです。
並べて見ることができないので、大きさはあまり感じられないかもしれませんね。
2月の満月は、アメリカの農事暦では「スノームーン」と呼ぶそうです。
昨夕の月
今晩は快晴の見込みです。美しい冬の月をお楽しみ下さい。
午後も快晴が続いています。
販売管理センター 6℃ 15:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 4.6℃ 15:00現在
こけもも平は、6.4度(14時20分)まで気温が上がりました。
明日までは穏やかな天気が続きそうです。
今日のセンター 13時半撮影
餌を置いていなかったのですが、バードケーキを食べにシジュウカラがやってきました
この後慌ててエサを出しました(笑)
- 更新日2023年02月04日
- カテゴリ四季の森だより
昨晩、外を覗いてみてびっくりしました。
雪が降っているではありませんか。
今朝はどれほど積もっているのかと思っていましたが、
雪は夜半に止んで、薄っすら積もった程度です。
日中は、路面の雪はほぼ解けていました。
気温も昨夜は暖かいかなと思っていたら、朝は意外と冷え込みました。
この時期は、寒気が強弱をつけながら続くことがあるので
朝見ると積雪ということがよくあります。
こけもも平の今朝の最低気温は-7.9度(6時)でした。
1時間気温データですので、もう少し下がった可能性があります。
今日はニュースの更新時間がありませんので、
画像のみご覧ください。
今朝の八ヶ岳
入笠山方面
八ヶ岳ズームライン
村道原村ペンション線
県道鉢巻線
まるやち湖
着雪した雪で木々が真っ白になっています
昼頃の八ヶ岳です
玉川地区から撮影 昼前から雲が多く出ていました
こけもも平(標高1500m)観測データ 3.8℃ 13:40現在 ※今日の最高気温
立春寒波で朝は冷え込みましたが、日中は気温が上がりました。
ただ、日差しが少なく、体感はそれほど暖かさを感じませんでした。
今日のセンター 13時半撮影
- 更新日2023年02月02日
- カテゴリ四季の森だより
昨日の午後から降り出した雪は夜中には上がったようですが、
今朝はやはり積雪していました。
センター付近で1cm弱、こけもも平で3cm程です。
規定の量ではありませんが、こけもも平は凍結も心配ですので除雪を行いました。
朝、別荘地付近では厳しい冷え込みになったものの、
市街地ではそれほどの冷え込みにはなりませんでしたが、
今日は身を切るような冷たい風が吹き付け、体感温度は低いです。
こけもも平の今朝の最低気温は、-8.9度(7時20分)でした。
今朝の八ヶ岳 今日は上空に薄い雲が出ています
入笠山方面
富士山 昨日よりははっきりと見えています
まるやち湖 寒いせいか今朝は1台も車がいませんでした
ベンチにも積雪しています
原村第2ペンションビレッジには、
12月18日に、コワーキングスペースがオープンしました。
1階には定員12~14人の共同スペースと会議室4室、
2階にはレンタルオフィス8室があり、最大40人ほどが利用可能です。
元はペンションだったこともあり、内装には木が多く使われ、薪ストーブもあるとの事です。
朝なので、中の画像は撮影できませんでしたが、落ち着いた雰囲気で仕事もはかどりそうです。
現在はプレオープン期間で、1日500円で利用できるようです。
四季の森からも近いので、山荘でリモートワークをされている皆様は
気分転換にこうした施設を利用されてみてはいかがでしょうか。
グランドオープンは春を予定しているそうです。
詳細は、リンク先にてご確認下さい。
センター駐車場 8時20分撮影
フロントガラスの雪
さて、今日は「No.2の日」だそうです。
2が並ぶことから制定されました。
山梨県南アルプス市に事務局を置く「日本No.2協会」が制定した記念日です。
こんな協会があることも初めて知りました。皆様ご存じでしたか。
記念日を通じて、様々な日本の第2位を知ってもらい、その魅力を高めるとともに
No.2仲間が交流し、地域観光などの新たな切り口として広くPRするのが目的だということです。
富士山に次いで2番目に高い山「北岳」があることから、南アルプス市に事務局があるんですね。
北岳の他に、琵琶湖に次いで大きい湖が「霞ヶ浦」、
札幌市の時計台に次いで古い時計台が「辰鼓楼(しんころう)」(兵庫県豊岡市)など、
No.1があるということは、当然No.2も存在します。
2番目は何かなと考えてみるのも楽しいですね。
ちなみに、日本で2番目に長い川は「利根川」、
2番目に大きい都道府県は「岩手県」、2番目に小さい都道府県は「大阪府」だそうです。
今日の別荘地内です。
からまつ平
からまつ平(立場林道)
しらかば平(村道)
しらかば平
こけもも平
こけもも平(蓼科山)
県道鉢巻線(天狗岳)
山荘の薪小屋のつらら 日々成長中
針葉樹に雪の花が咲いたようです
シカをみつけました
1頭だけだと思ったら、3頭います
北アルプス(こけもも平)
これわかりますでしょうか
風が強いので、木から雪が舞い落ちて、あたかも降雪しているようです
昼前から徐々に雲が厚みを増してきました。
このまま夜半まで雲りとなるようです。
寒気の流れ込みが強まったり弱まったりしているからでしょうか。
販売管理センター 0℃ 14:50現在
こけもも平(標高1500m)観測データ -0.6℃ 14:40現在
今日は寒い日中です。
午前中日が当たった場所は雪が解けましたが、
日陰はまだ残っています。
明朝は今朝より寒くなりそうですので、ご注意下さい。
今日のセンター 13時過撮影
飛行機雲が青空に映えます