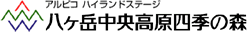四季の森ニュース

- 更新日2021年10月19日
- カテゴリ四季の森だより
昨晩は十三夜の月はご覧になれましたか。
昨日帰宅する際、四季の森周辺は晴れていて八ヶ岳もよく見えていたのですが、
私の自宅周辺では、低い雲が出て周辺の山々は全く見通せない状態でした。
何回か空を見上げてみたのですが、残念ながら月は見えませんでした。
四季の森周辺はどうだったんでしょうね。
10月20日の満月は見られるといいですね。
今日は昨晩からの雲が残っていましたが、八ヶ岳は見えていました。
曇りのため、昨日ほどの冷え込みはありませんでした。
こけもも平の観測データでは夜中の2時台に3.3度でしたが、
それ以降徐々に気温は上昇しています。
今朝の八ヶ岳 富士見町立沢地区の本郷小学校付近で撮影
山の色が変わっているのがおわかりになりますでしょうか。
この冷え込みで、遅れていた紅葉が山を下りはじめたようです。
立沢大規模水田地帯から見ますと、雲の境界がわかります。
入笠山方面
富士山方面は雲があり、裾野しか見ることができませんでした。
エノコログサも紅葉しています
もみの湯前のイチョウ
今日も水鳥たちの可愛い姿が撮れましたのでご覧ください。
思い思いの恰好のカルガモ 真ん中はカイツブリ
カイツブリとカルガモ
カルガモ
エサを探しているんでしょうか
羽ばたきの練習?
オオバンもいたのですが、カメラに収められませんでした。
まるやち湖
阿弥陀岳が白っぽく見えていたので拡大してみました。
一瞬雪かと思ったのですが、霧氷のようです。
綺麗ですね。
雪が積もるのも間近でしょうか。
午前中は、晴れて日が差していたのですが、
午後になり雲に覆われてきました。
別荘地内の様子です。
鉢巻道路
こけもも平
一瞬だけ阿弥陀岳が見えました
からまつ平
17時頃から雨が降り出しました。
暗くてよく見えないのですが、事務所内でも雨の音がしていますので、かなり本降りになっていますが、
予報は曇りなので、それほど雨量は増えないと思います。
こけもも平(標高1500m)観測データ 9.1℃ 17:00現在
今日のセンター
- 更新日2021年10月18日
- カテゴリ四季の森だより
昨日の雨上がりから空気が一変し、冷たい風が吹き、
今朝は放射冷却の影響で、冷え込みました。
こけもも平の観測データでは、6時50分に氷点下0.6度を観測しました。
今朝は、コートや手袋が必要になるほど寒いです。
北アルプスや東北地方などでは山々が冠雪したそうですが、
八ヶ岳や富士山は冠雪しなかったようです。
この時期は、山麓の樹木の緑色と紅葉の紅色、雪の白色の
「三段紅葉」と呼ばれる山を彩る3色の紅葉が楽しめる時期でもあります。
今朝の八ヶ岳方面 今朝も雲が出て山が見えませんでした
入笠山方面
富士山
北アルプス
画像から、キリリとした空気感が伝わるといいのですが。
さて、今朝のまるやち湖です。
湖面から湯気が立つ「気嵐(けあらし)」が見られました。
「気嵐」とは、冷たい空気が温かな水面の上にある時、
海だけでなく、川や湖からの水蒸気や、水面近くの空気が冷やされることで発生します。
「蒸気霧」、「蒸発霧」というものです。
少しアップして撮影
そして、今朝のまるやち湖はカルガモがたくさんいて賑やかでした。
とても活発に動き回っていました
カルガモたちは寒いくらいの温度が好きなのかもしれませんね。
さて、今日の夜は「十三夜」です。
「十三夜」は旧暦の9月13日から14日の夜のことをいいます。
「十五夜」は中国から伝わった風習なのに対し、「十三夜」は日本で始まった風習です。
「十三夜」のならわしは、後醍醐天皇(平安時代)が月見をしたのが始まりとも、
宇多天皇(平安時代)が十三夜の月を愛でたのが始まりとも言われています。
平安時代の書物には、宴が催されたということが記されていて、
その頃から親しまれていた風習だったようです。
なぜ、満月ではなく、少し欠けている月を見るのかとも思うのですが、
十三夜の解説を見ますと、定かな説というのはないのですが、
完璧ではない未完成ゆえの美しさが、
日本人の心に響いたからと考えられているそうです。
これから欠けていく月よりも、
もう少しで満ちる月に何かしらの思いを込めていたのかもしれないですね。
今夜の原村の天気は晴れの予報です。
澄んだ空気で十三夜の月はより一層美しく見えることでしょう。
皆様も寒いですが外に出て月を眺めてみませんか。
昨晩の月
こけもも平から見る阿弥陀岳です。(12時頃撮影)
まだ雲がありましたが、山はくっきりと見えていました。
雪はなさそうですね。
今日はよく晴れているのですが、気温が上がりません。
日差しがあるのに寒い1日です。
販売管理センター 14℃ 14:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 10.1℃ 13:50現在
急に気温が下がりましたので、体調を崩さないようお気をつけ下さい。
今日のセンター
今年は柿の実りが悪いようです
- 更新日2021年10月16日
- カテゴリオーナー様へ
今朝は雲が広がり、時折霧雨が降るような天気でした。
今日はこのまま曇りなのかと思っていましたら、
雲がとれて秋晴れになりました。
富士見町立沢地区大規模水田地帯は霧の中でした
標高1000m付近には霧が発生していましたが、
もみの木荘付近まで上がってくると霧もなく、青空も少し見えていました。
もみの湯バス停のイチョウ
曇っていたためか、気温も比較的高く、寒さは感じません。
週間天気予報によりますと、
暑さは今日までで、
これから低気圧と高気圧が交互にやってきて、一気に季節が進み、
19日(火)は11月下旬から12月初旬並みに寒くなるそうです。
そろそろ山荘の水道の凍結防止の対策をしていただく時期になりました。
センターで承っております水抜き作業ですが、
スタッフがシフト制となっており、急な対応ができませんので、
早めに連絡をいただけますようお願い申し上げます。
寒くなるのはイヤですが、紅葉が美しくなるのはいいですね。
今年は秋になっても暖かく、紅葉が進んでいませんので、
一気に色づいてくるかもしれません。
今朝は八ヶ岳が見えませんでしたので、
茅野市へ出向いた際に撮影してみました。
南八ヶ岳 原保育園付近より撮影
北八ヶ岳
画像手前は、稲をはぜ掛け干しにしている田んぼです。
はぜというのは、木の棒を2・3本組み合わせて支柱をいくつか作り、
そこへ長い竹竿のような丈夫な棒を渡して作ります。
その長い竹竿に束ねた稲穂を掛け、自然にゆっくりお米を乾燥させます。
天日に干すことで、アミノ酸と糖の含有量高くなり、
稲を逆さまに吊るすことで、わらの中の油分や栄養分、甘味が下りてきて
旨味が増すと言われています。
最近では「はぜ掛け米」と呼ばれ、他のお米とは差別化されています。
稲刈りは大型のコンバインで行うことが多くなり、
こうした光景を見かけることが減ってきました。
伝統的なやり方は手間も労力もかかり大変ですが、美味しいお米になるんですね。
まるやち湖 14時頃撮影
まるやち湖裏手の「しらかばの小径」
しらかばの葉が落ちてきたのでヤドリキが目立つようになってきました。
通勤途上の花々です。
マリーゴールド
ドーム菊
ガウラ
宿根アスター
ヘリクリサム
午後も夕方までは秋晴れが続き、暖かな日中でしたが、
今晩から雨が降ってくるようです。
こけもも平(標高1500m)観測データ 20.3℃ 14:40現在
今日のセンター
センター入口のヤマザクラの葉は、残り数枚になりました
- 更新日2021年10月14日
- カテゴリ四季の森だより
昨日は夜までよく降りました。
今日は朝から晴れるのかと思ったのですが、
朝のうちはまだ雲が多く、周辺の山々を見ることができませんでした。
今朝は、鉢巻道路を通ってみました。
富士見高原リゾート付近 まだ色づき始めといった感じですね
ヨドバシカメラ保養所付近
カントリーキッチンを過ぎた付近
晴れていれば、さらに美しく見えると思います。
小淵沢インターチェンジから鉢巻道路を通って四季の森まで、
美しい紅葉を見ながらドライブできます。
くれぐれも脇見運転はしないようご注意下さい(笑)
さて、今日は「鉄道の日」だそうです。
1872(明治5)年9月12日(新暦10月14日)に、
新橋駅から横浜駅を結んだ日本発の鉄道が開業したことが由来となっています。
元々は、1922(大正11)年に「鉄道記念日」として制定されたのですが、
国鉄色が強いということで 1994(平成6)年に「鉄道の日」に改称されました。
国土交通省によりますと、
「鉄道が国民に広く愛され、その役割についての理解と関心がより深めること」
ということを目的に記念日としたそうです。
当社グループのアルピコ交通では、松本駅から新島々駅までの「上高地線」を運行しています。
現在は、お盆の長雨で田川にかかる橋りょうが被災してしまい、
一部区間が、バスによる代行輸送となっていますが、
上高地も紅葉の最盛期を迎えていますので、
お出掛けの折は是非上高地線をご利用下さい。
上高地線
京王井の頭線3000系の車両が使われています。
今朝のまるやち湖です。
紅葉は少しずつ進んでいます。
八ヶ岳自然文化園入口のモミジ 道路に面したところだけ一段と鮮やかに染まっています
全部同じ色ではないのがいいですね
村道原村ペンション線沿いの黄金アカシア
朝の雲は徐々にとれて、青空が広がっている本日です。
気温も上がり、この時期としてはとても暖かいです。
販売管理センター 19.5℃ 16:50現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 14.0℃ 16:50現在
明日も晴れの予報です。
土曜日の夕方から日曜日の午前中にかけて雨になり、
それを過ぎると気温は平年並みになるそうです。
衣替えなど、明日の晴れを有効に使いたいですね。
今日のセンター
カラマツも少しずつ色づき、シラカバの葉も少なくなってきました
- 更新日2021年10月13日
- カテゴリ四季の森だより
今朝は雷が鳴り激しい雨が降った時間帯もありました。
通勤時間帯には雷も聞こえなくなったのでホッとしました。
四季の森周辺は霧に包まれていて、強くなったり弱くなったりを繰り返しながら
雨は続いています。
今朝のまるやち湖
霧でピントが合わないので、こんな画像になってしまいました
もみの湯バス停のイチョウ
村道(原村ペンション線)
鉢巻道路
さて、昨年も取り上げたのですが、今日は「さつまいもの日」なのだそうです。
サツマイモの産地である埼玉県川越市の「川越いも友の会」が制定しました。
昨今のサツマイモは「安納いも」や「紅はるか」などしっとり系で甘味の強いサツマイモが主流になってきていますが、
私はホクホク系が好みで、先日「黄金千貫」という種類のサツマイモをお取り寄せしてみました。
芋焼酎の原材に使われる代表格の品種としても知られていますが、
栗と同じようにとてもホクホクとしますが、甘味は少なめです。
ベニアズマほどずっしり目が詰まっている感じではありません。
資料によりますと、黄金千貫はでん粉の粒子が細かく舌ざわりもよいということです。
黄金千貫の名前の由来は、「黄金色のイモがザクザク採れる」とか
「黄金を千貫積むほど価値のあるイモ」といったことからだと言われているようです。
また、黄金千貫で作られて芋焼酎は、ふんわりとやさしい香りとキレのよい甘味が特徴で、
バランスがいいそうです。
黄金千貫
ホクホク系がお好みだという方は、ぜひ「黄金千貫」を食べてみて下さい。
サツマイモは苦手という方は芋焼酎を飲んで季節感を味わってもよさそうですね。
今日は雨なので、紅葉も色鮮やかになっています。
別荘地内の様子をご覧ください。
からまつ平
からまつ平
ブナ
黄金アカシア
しらかば平
しらかば平
しらかば平
モミジ
こけもも平
ヤマウルシ
ハウチワカエデ
こけもも平
トチノキ
ドウダンツツジ
マユミ
モミジ
全体的にはまだ色づきはこれからですが、
個々に見ると、色合いがとても美しくなっています。
販売管理センター 18.5℃ 15:30現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 14.8℃ 15:30現在
今日のセンター
ノブドウ