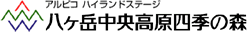四季の森ニュース

- 更新日2021年02月19日
- カテゴリ四季の森だより
今朝も冷え込みは厳しかったのですが、昨日までの真冬の天気とは打って変わり、
風もそれほどなく、気温はぐんぐん上がっています。
空は快晴で、絶好のお天気です。
こけもも平の今朝の最低気温 -12.6℃ 5:00観測
今朝の八ヶ岳
富士見パノラマスキー場
今朝の富士山
さて、一昨日から昨日の朝にかけて雪が降った四季の森周辺ですが、真冬日が数日続いていました。
昨日のこけもも平の観測地点では、最低気温が氷点下14度を記録しています。
今朝の周辺道路は、一旦融けた雪がカチカチに凍っていましたが、
日当たりの少ない場所は、まだサラサラの雪が楽しめます。
別荘地内道路は、午前中の時点では凍っているというよりは圧雪状態です。
スタットレスタイヤで4WDの車両でしたら、走行に問題ありません。
周辺道路の様子です。風景とともにご覧下さい。
鉢巻道路
立場林道
しらかば平入口(村道)
共用道路
別荘地内の様子もご覧下さい。
からまつ平
しらかば平
しらかば平
こけもも平
こけもも平
今日の暖かさで融け出した雪が明朝は凍結して滑りやすくなりますので、お気をつけ下さい。
今日は雲ひとつない空が広がっていて、絶好の撮影日和です。
カメラマンの方が撮影をしているのを多く見かけました。
周辺の風景をお楽しみ下さい。
八ヶ岳 芹ケ沢付近から撮影
蓼科山と北横岳
茅野市街と北アルプス 茅野市豊平付近より撮影
八ヶ岳中央農業実践大学校からの八ヶ岳
八ヶ岳自然文化園横「白樺の小径」
まるやち湖
まるやち湖には、またまた小動物の足跡が
キツネでしょうか
土手や駐車場の雪はまだサラサラです
数日間寒さで凍えていた四季の森ですが、耐えたご褒美のような本日の陽気です。
なんだか鳥の声もよく聞こえるような気がします。
販売管理センター 5℃ 15:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 3.6℃ 14:40現在
今日はこけもも平もプラスの気温になりました。
しばらくはお天気が続くようです。早く雪解けしてくれるといいですね。
今日のセンター
車にもツララが
- 更新日2021年02月17日
- カテゴリ四季の森だより
強い寒気の流れ込みがあり、四季の森周辺では雪が降っています。
朝の時点では5㎝程だったのですが、見通しが悪くなるほど降る時間帯があるなど、
断続的に積雪が続き、かなり大雪になっています。
こけもも平は午前中除雪を行いました。
午後は全ての区画で除雪を行う予定です。
天気予報では、午後には雪が止むというような予報でしたが、どうでしょうか。
夕方まで続きますと、かなりの積雪量になりますので、どうぞご注意下さい。
こけもも平の今朝の最低気温 -7.8℃ 11:10観測
朝は氷点下6度前後だったのですが、気温は下がってきています。
今日はセンター付近でも真冬日になりそうです。
今朝の八ヶ岳方面 8時頃撮影
深山地区環境保全林 8時頃撮影
以下、11時15分頃撮影です。
鉢巻道路
立場林道
しらかば平入口(村道)
からまつ平
午後の出動を待つ除雪車
2月17日は、「天使の囁きの日」の記念日です。
天使の囁きとは、ダイヤモンドダストのことです。
1978(昭和53)年のこの日、北海道幌加内町母子里の北演習林で、氷点下41.2度という最低気温が観測されました。
ただこの記録は、気象庁の公式記録からは外れていたため、1902(明治35)年に旭川で記録された氷点下41.0度が
公式の日本最低気温となっているようです。
そんな極寒のイメージをプラスに転じようと、地元の人々により制定された記念日が「天使の囁きの日」なのだそうです。
2月は、寒い日と暖かい日の差が大きく、ものすごく冷え込む日もあるので侮れません。
今日のように、南岸低気圧でもないのに大雪になるケースもあるんですね。
販売管理センター -3℃ 13:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ -7.4℃ 13:00現在
まだ雪は続いていますが、13時を過ぎた頃から小降りになり、
時折、強い風で木々に積もった雪や屋根の雪が舞い上がってホワイトアウトになっています。
今日の雪はとても軽い雪ですが、、ふわふわな状態でセンター付近で15㎝弱の積雪です。
こけもも平は20㎝程にはなっていると思われます。
今日のセンター
こけもも平は、雪の下は氷です。
- 更新日2021年02月16日
- カテゴリ四季の森だより
今日は、真冬の寒さに戻ってしまった四季の森です。
昨日心配していた道路の凍結は、日影や水溜まりなど限られていてホッとしました。
ただ昨晩からの強風で、落枝があちこちで見られましたが、
別荘地内では、特に倒木等は発生しておりません。
また、朝は少し吹雪いたりしていたのですが、積雪するほどではありませんでした。
こけもも平の今朝の最低気温 -4.1℃ 7:00観測
今朝の八ヶ岳
立沢大規模水田地帯は、さえぎるものがないのでとても風が強く、強風で雪が路面を漂っていました。
富士見パノラマスキー場方面
さて、今日は「寒天の日」です。
茅野市の名産品は、角寒天(棒寒天)です。
NHK「ためしてガッテン!」の番組で、寒天には、血糖値や血圧等の数値を下げるのに有効な食品だと取り上げられたため、
その放送日を「寒天の日」として、茅野商工会議所と長野県寒天水産加工業協同組合とで定めました。
12月初旬から始まっていた寒天製造は、2月中旬にはほぼ終了していますが、
今年は早くから寒さが継続したため、寒天製造は順調で品質もよいということです。
長野日報 2月14日記事
※ ↑ クリックで拡大します
今日は、「寒天の日」で、給食で寒天メニューを提供する学校も多く、原小学校では「牛乳かん」が出されるそうです。
牛乳かんなど寒天で固めた料理を、諏訪地方では「天寄せ」と呼びます。
「天寄せ」は諏訪地方のソウルフードで、冠婚葬祭などでは欠かせない1品です。
昔は砂糖を入れただけの無職透明なものだったのですが、色をつけたり、くるみや豆腐や溶き卵を入れたり
「手前天寄せ」と呼ばれるほど、それぞれの家庭ごと中に入れる具材も変わってきます。
塩ようかんにも角寒天が使われます
寒天の最大の特徴は、なんといっても食物繊維の豊富さです。
乾燥状態では80%を超えるほどの食物繊維を含み、あらゆる食材の中でも抜群の含有量を誇っています。
また、食物繊維には水溶性と不溶性の2種類ありますが、寒天にはその両方が含まれているんですね。
そのため、腸の動きを活発にするので、美容と健康によいと言われています。
実際に寒天を摂取し、コレステロール値や血糖値などの改善が実証されていますが、
寒天の摂取を止めてしまうと、1ヶ月ほどで元の数値に戻ってしまうようなので、
日常的に摂りたい食品ですね。
長野県寒天水産加工業協同組合のホームページには、寒天のレシピが多く掲載されていますのでご活用下さい。
長野県寒天水産加工協同組合 → こちら
茅野市宮川にある寒天蔵
寒天製造が盛んになった際、原材料や製品を保管しておく収納場所が必要となったため
製糸業が衰退しつつあった岡谷から、繭を保管するための繭蔵がいくつも茅野へ移築されました。
この蔵もそのひとつです。立派な建物ですね。
現在は寒天蔵としての役目は終えてしまいましたが、地元商業会の方々の手で多目的ホールとして生まれ変わり、
寄席やコンサートなどのイベントが行われています。
今朝のまるやち湖の様子です。
駐車場から見た空
午後になり、風は強いままですが、安定して日差しが届くようになりました。
ただ、強風で体感温度は低いです。
風が収まってくれるといいのですが。
販売管理センター 1℃ 14:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ -1.5℃ 14:00現在
昨日までの暖かさから一転、今日は真冬日のこけもも平です。
今日のセンター
- 更新日2021年02月15日
- カテゴリ四季の森だより
今日は、とても暖かかい朝だったので、絶対雪は降っていないだろうと、ライブカメラを確認せず出勤しました。
予想通り、雪ではなく雨が降っている四季の森です。
樅の湯辺りまでは非常に濃い霧が発生していましたが、樅の湯を過ぎると霧も少しずつ減って
見通しもよくなっていました。
今日は夕方まで雨が続くようです。
こけもも平の今朝の最低気温 1.9℃ 5:00観測
こけもも平の観測地点でも昨晩から氷点下にはなっていません。
立沢大規模水田地帯で、八ヶ岳方面を撮影しました。8時頃の様子です。
深い霧に包まれ、見通しが悪くなっています。
立沢大規模水田地帯では、穏やかな陽気だった週末に多くの田んぼで土手草焼きが行われたようです。
外に出てみると、焦げ臭いがまだ立ち込めていました。
一昨日の夜は大きな地震がありましたね。
原村役場でも震度3を観測しました。
東日本大震災の余震だという発表でしたが、10年も過ぎたのにまだこんなに大きな余震が起こるんですね。
本当に怖いです。
政府の地震調査委員会によりますと、余震はまだ10年は続くとの見解を示しています。
揺れの被害だけでなく、停電や断水といった生活インフラが使えなくなった場合の対策など、
改めて考えておかなくてはいけないですね。
今朝の周辺の様子です。
鉢巻道路(富士見方面)
鉢巻道路(学林方面)
しらかば平入口(村道)
森林軌道見学者駐車場
立場林道の歩道 雨で余計に滑りやすくなっていますご注意下さい
さて今日は、日本海側と太平洋側の2つの低気圧に挟まれた気圧配置になっています。
これを「二つ玉低気圧」と呼ぶようなのですが、
冬から春にかけて比較的多く見られ、2つの低気圧が日本列島を挟むように進んでいきます。
二つ玉低気圧は、スピードが速い、急速に発達し広い範囲に風雨や風雪をもたらす、東海上でまとまりさらに発達する、
というような特徴があるそうです。
特に2つの低気圧がまとまると、北からの寒気と南からの暖気がぶつかって急速に発達し、爆弾低気圧と呼ばれる
暴風を伴った荒れた天候になるので注意が必要だということです。
突風が吹き荒れるような天候にならないといいのですが。
今朝のまるやち湖の様子です。
雨ですが、まだ全面結氷しています
東側の斜面はまだ雪が多いです
朝はそれほど強く降っていなかった雨ですが、
昼前後には、室内にいても雨音がするほど本降りになったものの、また小降りに戻りました。
これが雪でなくてよかったです。
販売管理センター 6℃ 13:30現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 2.7℃ 13:20現在
気温は12時半を過ぎた頃から徐々に下がってきています。
今日の夕方には雨は止むとの予報ですが、明朝の凍結が心配です。どうぞご注意下さい。
今日のセンター
- 更新日2021年02月13日
- カテゴリ四季の森だより
今朝は、冷え込みも少なく、朝から暖かな陽気になっています。
今日は桜が咲く頃のような暖かさになるようです。四季の森は何度まで上がるでしょうか。
こけもも平の今朝の最低気温 -1.3℃ 4:00観測
今朝の八ヶ岳
今朝は北アルプスもくっきりしています
富士山方面は雲が少し出ていました
昨日見えていました編笠山の雪形
上り鯉 下り鯉
この雪形が現れると、そろそろ冬も終盤となり農作業の開始の目安とされているのですが、
立沢大規模水田地帯では、土手焼きが始まっています。
今日は、風もなく穏やかな陽気なので、多くの田んぼで行われるかもしれません。
土手草を焼く理由は、害虫とその卵の駆除、酸性となった土壌の中和、腐りにくい枯草の除去、
火災の予防の観点から行われています。
また、焼いた灰が、土手に新たに生えてくる土手草の肥料となるとも言われています。
土手草がしっかり生えることで、土手をしっかり固めて崩れるのを守ってくれているんですね。
さて、明日はバレンタインデーです。
節分・立春が終わりお正月からの年中行事も一段落すると、次にバレンタインデーがやってきますね。
関係ない、とかチョコは苦手という方もいらっしゃると思いますが、巷にはチョコレートがあふれている時期です。
菓子メーカーでも初冬から新商品を発売したり、和菓子屋さんでもバレンタイン限定商品なども出回るので、
いろいろ試してみたくなってしまう、チョコレートの季節。
チョコレートは太るとかニキビができるとか健康に悪いようなマイナスのイメージもあるのですが、
健康に良い成分も多く含まれているんです。
チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、血液をサラサラに保つ働きがあり、
動脈硬化のリスク低減に効果的と言われています。
また、チョコレートの中には食物繊維のグリニンが含まれていて、
これが腸のぜん動運動を活発にすることで便通を良くし、腸内環境を整えます。
また、テオブロミンという成分はリラックス効果があると言われているのですが、
テオブロミンは過剰に摂りすぎると、利尿作用や興奮作用高めてしまうことがあるので、食べ過ぎには注意が必要です。
チョコレートは脂質や糖質も多く含まれているので、カカオの含有量が多いものを選ぶとよいかもしれません。
美味しいものは少しだけ、がいいようですね。
今日は陽気が暖かく、鳥たちも森でのんびり過ごしているようです。
通勤途上で、
ムクドリ(オス)を見つけました
こちらは同じ木にいるムクドリのメスだと思われます
群れのイメージが強いムクドリですが、今日はつがいで行動していました。
別荘地内では
キジ(オス)が歩いていました
鳥も、穏やかな陽気の時は動きもゆるやかな気がします。
おかげで、私でも撮影ができるんです(笑)
別荘地内は、山荘の敷地内、路肩など雪が多く残っていますが、しらかば平、からまつ平の道路は、
ほぼ路面が見えて車の走行には支障がなくなってきました。
こけもも平については標高が高く、降る雪の量も違うため、
日当たりのよい場所を除き、まだ道路は凍結しているところが大半です。
こけもも平の本日の様子です。
北アルプスまでよく見えています。
1・2区画からの阿弥陀岳
ゴミステーション付近
森の中
共用道路
販売管理センター 12℃ 14.00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 9.0℃ 14:00現在
こけもも平でも、10度に迫るほど暖かくなりました。
明日も暖かくなるようです。
今日のセンター
今朝のまるやち湖