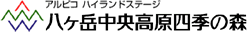四季の森ニュース

- 更新日2022年01月13日
- カテゴリ四季の森だより
今日は、強い冬型の気圧配置で、寒気が流れ込んできているため
朝から雲が広がっています。
朝のうちは青空も見えていたのですが、段々雲が低くなり、昼前から雪が舞っています。
時折強く降って、地面が白くなりますが、
空が明るく薄日が差す時間帯もあり、積雪量は増えていません。
今朝の冷え込みも厳しく、朝の道路はガチガチでした。
こけもも平は、3時台に-11.5度、7時台に-10.2度でした。
一番冷え込んだのは0時台で、-12.0度まで下がっています。
今年は雪が多く一段と寒いシーズンですね。
今朝の八ヶ岳 朝は八ヶ岳は少し見えていました
入笠山方面
富士山
さて、雪が降り屋根の上にも積もっていますが、寒さ厳しいためすぐには融けません。
それでも、真冬日であっても屋根の雪は少しずつ融けて水滴として落ちてきます。
そして夜間に再び凍りついて棒状に伸びた氷が氷柱(つらら)です。
普通はまっすぐ下に伸びますが、風が強かったり、屋根の雪に押されたりすると
斜めに伸びていくという場合もあります。
そして、寒暖差が繰り返されることで徐々に長くなっていきます。
つららの語源は、古来、氷などの表面がツルツルして光沢のあるものを
「連連(つらつら)」と呼んでいたものが転じたと言われています。
東北などでは、かつて「垂氷(たるひ)」と呼ばれていたとか。
つららは、お天気がよければキラキラしてとても神秘的で美しく感じられ、
私も見つけると嬉しくなるのですが、
ロシアでは毎年600人以上の人がつららの落下で死亡しているそうです。
ロシアの内陸部では-50度にもなるところもあると聞きますので、
つららは想像もつかない大きさなのでしょうが、恐いですね。
そして、こんな風に雪が固まり、屋根からせり出して垂れ下がるのを「雪庇(せっぴ)」といいます。
このように丸くなることもあります。
つららも雪庇も落ちてくると大変危険です。
真下を歩かないように頭上にもご注意下さいね。
氷つながりということで、今日は原小学校のスケートリンクを見てきました。
雪が降りましたが、綺麗に整備されています。
今日は白旗で、滑走可能なのですが、
小学校は新型コロナウイルスの影響で休校になってしまいました。
早く子供たちの姿が戻ってくるといいですね。
今日の別荘地内です。
からまつ平(立場林道)
しらかば平
こけもも平
こけもも平では、木々に積もった雪がまだ残っていて、
雪が降った直後のような風景を楽しめます。
標高1500m付近
雪の花が咲いているよう
繭玉を木にさした「餅花」のようにも見えますね
今日も四季の森は真冬日でしたが、
15時を過ぎた頃から雪は止み、青空が見えるようになり時々日も差すようになってきました。
販売管理センター -1.0℃ 16:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ -6.7℃ 16:00現在
こけもも平の今日の最高気温は-5.2度(13時半)でした。
寒くてもいいので、このまま晴れてくれるといいのですが、
天気予報を見ますと、夜遅くに雪が降るようです。
冬型の雪なのでそれほどの降雪量にはならないと思うのですが、
寒気の流れ込み具合で積雪量が多くなる場合もありますので、どうぞご注意下さい。
今日のセンター
- 更新日2022年01月12日
- カテゴリ四季の森だより
昨日は1日雪降りになりました。
南岸低気圧の湿った雪で、今朝は厳しい冷え込みでしたので、
道路はガチガチ・バリバリな状態で非常に危険でした。
おまけに今日は朝イチで外出の予定があり、車の雪を下ろそうとしたのですが、
車両は凍りついていて、ドアも窓も開かなかったので、
あまりやりたくはなかったのですが、スノーブラシでガリガリと削りました。
太陽が出てくれば自然と融けるのですが、朝のうちはまだ日差しも期待できず、
お湯も沸いていなかったので、とても苦労しました。
こけもも平の今朝の最低気温 -10.5℃(8時台)
今朝の八ヶ岳 まだ吹雪いているようです
入笠山方面
富士山 今日は風が強いのですが、富士山も強い風が吹いているようです
さて、周辺道路ですが、
八ヶ岳エコーラインは除雪されていましたが、
八ヶ岳ズームラインは朝の時点ではまだ除雪されていませんでした。
八ヶ岳ズームライン(八ヶ岳エコーラインとの交差点付近)
八ヶ岳ズームライン(鉢巻道路側)
鉢巻道路 除雪されています
村道(原村ペンション線)も今朝は除雪されていました
別荘地内の様子もご覧ください。
からまつ平
からまつ平
立場林道
しらかば平
しらかば平
シカがいました
一之瀬堰
花が咲いているようです
鉢巻道路
こけもも平入口
こけもも平
枝についた雪が舞い落ちて、風が強いので時折雪煙になります
こけもも平
こけもも平
こけもも平の最高地点
こけもも平沈砂池
共用道路
別荘地内は、昨日も除雪を行いましたが、
引き続き今日も除雪、拡幅作業を実施しています。
今年は雪が続きますね。
硬く重い雪なので、重機の力が頼りになります。
今日は晴れているものの、気温は上がらず真冬日ですが、
日差しは強く、日当たりのよい場所は雪が融けています。
販売管理センター -2.5℃ 15:20現在
こけもも平(標高1500m)観測データ -7.1℃ 15:10現在
今日のこけもも平の最高気温は、-5.6度(13時半)でした。
太陽光が眩しいくらいで暖かそうに見えるのですが、
外に出ると身を切るような風が吹きつけ非常に寒い本日です。
明日も天気はよさそうですが、冷え込みは厳しくなりそうです。
暖かくしてお過ごし下さい。
今日のセンター
跳ね上がった雪が凍りついています
- 更新日2022年01月11日
- カテゴリオーナー様へ
1/11こけもも平ごみステーション前にごみが3箱不法に投棄されていました。
心当たりのある方は今後不法投棄はおやめください。
ごみステーションの鍵を忘れた場合はセンターにご相談ください。
また、可燃ごみは原村指定袋に入れてゴミ出ししてください。センターでも販売しています。
段ボールとその他の紙は分けてください。段ボールは資源ごみとして回収、その他の紙は燃えるごみとしてお出しください。
みんなが気持ちよく利用できるようご協力お願いいたします。
- 更新日2022年01月10日
- カテゴリ四季の森だより
今朝は、通勤途上で八ヶ岳や入笠山も見えていたところもあったものの
撮影ポイントは霧の中でした。
入笠山方面にはいつもより高い位置に雲海が見えていたので、
霧が出ていた場所は雲海の中だったと思われます。
今朝も寒い朝でしたが、昨日と同じようにプラスの気温になっています。
こけもも平の今日の最低気温 -6.6℃(7時台)
朝は霧のため山々は見えませんでした。
村道(原村ペンション線)
鉢巻道路
霧が発生していたので、もしやと思いながら走行していると、
まるやち湖では見られませんでしたが、
上の画像で少しおわかりかと思いますが、樹霜が見られました。
背景がグレーですと、分かり難いですが枝にはびっしり霜がついてます
8時半頃から霧が晴れて、青空とのコントラストが美しく見られました。
日が当たるとあっという間に消えてしまうはかない樹霜です
今朝の樹霜は、センター付近が一番綺麗でした。
今朝の立沢大規模水田地帯では、標識に鳥が留まっていました。
ノスリのようです。猛禽類ですが、ずんぐりとした姿が可愛いらしいです。
ノスリは人間をあまり怖がらず、気にしない傾向があるので、
こんなに近くで撮影できるんですね。
カメラを向けると、ポールに飛び移り、またカメラを向けると、
違う標識に移動してしまいました。
人を気にしない傾向の鳥ですが、近づきすぎると逃げます。
逃げない適度な距離感というのがなかなか難しいです。
冬毛なのかモフモフですね
そして、今日の別荘地内です。
立場林道
しらかば平
こけもも平
北アルプス(こけもも平)
今日は蓼科へも出向きました。
無藝荘
蓼科湖(蓼科山、北横岳)
湖は半分凍っています
水鳥たちは氷の上で小休止
帰りに、茅野市玉川地区から八ヶ岳を撮影しました。
南八ヶ岳
北八ヶ岳
まるやち湖
駐車場にはどんど焼きのやぐらの準備ができていました
今日は成人の日ですね。
原村の成人式は1月3日に終わっていますが、
昨年は式が中止されたため、午前中は昨年、午後は今年の新成人の式が行われました。
原村では、例年大勢の新成人が参加できるようお正月に開催しているんですね。
成人の日というと、天気が荒れるというようなイメージがありますが、
今年は穏やかないい天候に恵まれました。
販売管理センター 6℃ 14:50現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 1.8℃ 14:50現在
こけもも平の今日の最高気温は、2.6℃(14時20分)で、今日もプラスの気温になりました。
明日の日中は雪マークが出ています。今のところそれほどの降雪の予報はありませんが、
天気予報は順次更新されますので、最新の情報をご確認下さい。
今日のセンター
道路の雪も融けてシャーベット状です
- 更新日2022年01月09日
- カテゴリ四季の森だより
今朝も寒かったのですが、昨日よりは冷え込みは少なく、
こけもも平は-6.7度(6時台)を観測しています。
朝から晴れていますが、薄い雲が広がり、昨日のような快晴とまではいきませんが、
日差しは暖かく、こけもも平でも午前中からプラスの気温になっています。
今朝の八ヶ岳
今朝は八ヶ岳全体が見渡せる場所を探してウロウロしたのですが、
ハウスなどの構築物が入らないで撮影できるところがなかなか見当たらず、
結局、深山農村公園から撮影しました。
富士山
実は富士山も、富士見町立沢地区のいつもの場所で撮影しようと思っていたのですが、
先客があってダメだったので、少し位置をずらしての撮影です。
西側の山々もよく見えていましたが、北アルプスは雲が出ていました。
今朝のまるやち湖
まるやち湖の駐車場は、
原村ペンション・原山地区のどんど焼きの準備のため駐車できない場所ができています。
どんど焼きは、1月16日(日)19時から行われます。
さて、原村第2ペンションビレッジ内には、
昨年11月中旬にオープンした建物があり、何かのショップなのかと思っていたのですが、
確認したところ、一棟貸しの宿泊施設でした。
その名も「八ヶ岳リトルビレッジホテル」。
ネットの情報などを見ますと、
建物は客室で、村全体がホテルの舞台というコンセプトになっているようです。
タイニーハウス4棟が建てられていて、今朝も1棟は利用されているようでした。
タイニーハウスは、アメリカの発祥で現在日本でもにわかに注目を集めているとか。
タイニー(とても小さい)ハウス(家)ということで、日本語では小屋という意味になります。
大きさには明確な基準はないようですが、20㎡とか10坪といった単位でよく使われているそうなので、
かなりコンパクトな物件ですね。
アメリカでは「大きな家」が幸せのシンボルでしたが、
大規模災害やサブプライムショックなど、家について考える出来事が続き、
本当に大きな家が必要なのか、大きな家が幸せにつながるのかという新しい気づきから、
物を持ちすぎず、シンプルに暮らすという考え方が少しずつ浸透し、
ミニマルな暮らしを実現する形のひとつとして、
今では世界的な広がりになっているのだそうです。
この宿泊施設の建物もそれぞれ20㎡ほどになるそうですが、
各棟にミニキッチン、シャワールーム、Wi-Fiが備えられているほか、
建物周りの砂利スペースで焚火やテントも利用もできるそうです。
また、基本素泊まりですが、希望があれば食材も手配をしてもらえるようです。
別荘地の購入を検討しているが、この時期はどんな気候なのか、周辺はどんな様子なのかなど
事前のリサーチに、こうした宿泊施設を利用して
暮らしの実体験をしてみるのもいいかもしれませんね。
八ヶ岳リトルビレッジホテル → こちら
午後も全体的に薄い雲が広がっていますが、日差しを遮るようなものではありません。
風もなく穏やかな日中で、気温も上がりました。
販売管理センター 6℃ 14:00現在
こけもも平(標高1500m)観測データ 3.2℃ 14:00現在
明日も穏やかな陽気が続くようです。
新型コロナウィルスの感染者が急増し、いよいよ第6波ということでしょうか。
今回のオミクロン株は感染力が非常に強いようで、どこまで増えるのか心配になります。
長野県内でもオミクロン株の陽性者が確認され、
諏訪圏域は、現在長野県内の警戒レベル「3」(警報)となっています。
基本的な感染対策をしっかり行っていきましょう。
今日のセンター